多くの日本企業では、システムアドミニストレーターすら専任で配置せず、ITに詳しい社員が兼任している現状があります。いわゆる「一人シスアド」と呼ばれる状況は、多くの書籍や記事で問題点が指摘されています。IT投資の重要性が十分に認識されていないことが原因の一つですが、グローバルな視点で見ると、この状況はあまりにも時代遅れと言わざるを得ません。
なぜ今、社内エンジニアが必要なのか
現代のビジネス環境において、売上分析、広告戦略、財務、管理、総務、企画といったあらゆる業務は、パソコンやソフトウェアを活用して進められるのが当たり前です。しかし、これらのソフトウェアは高度化、細分化、多様化の一途をたどっており、それらを適切に組み合わせ、目的とする資料や成果物を作成するための労力は、かつてないほど増大しています。
例えば、マーケティング部門では、顧客管理システム(CRM)、広告配信プラットフォーム、アクセス解析ツールなど、複数のツールを連携させてキャンペーンの効果測定を行う必要があります。それぞれのツールからデータを抽出し、統合し、分析する作業は、専門的な知識とスキルがなければ非常に困難です。また、経理部門では、会計システム、給与計算システム、経費精算システムなどを連携させ、月次決算や年次決算を効率的に行う必要があります。これらのシステム間のデータ連携やカスタマイズは、高度なITスキルを必要とします。
このような状況において、社内エンジニアこそが、部門を横断的に活用できるツールやシステムを提供し、業務効率化を推進する役割を担うことができるのです。

社内エンジニアと外部エンジニアの違い
ここで重要なのは、外部エンジニアではなく、社内エンジニアを設置することの意義です。外部エンジニアは、確かに高い技術力を持っていますが、社内の業務プロセスや組織構造に関する知識が不足しています。そのため、外部エンジニアにシステム開発を依頼する場合、業務要件の定義やコミュニケーションに時間がかかり、結果的にコストが増大する可能性があります。
一方、社内エンジニアは、日々の業務を通じて、社内のニーズや課題を深く理解しています。そのため、業務をシステム化する際に、現場の意見を迅速かつ的確に反映させることができ、より実用的で効果的なツールやシステムを開発することが可能です。
例えば、ある中小企業では、これまで手作業で行っていた顧客情報の管理をシステム化するために、外部のIT企業にシステム開発を依頼しました。しかし、完成したシステムは、現場のニーズに合致せず、ほとんど利用されませんでした。その後、社内にエンジニアを採用し、現場の意見を聞きながらシステムを再構築したところ、顧客情報の管理が大幅に効率化され、営業部門の売上向上にも貢献しました。

社内エンジニアによる生産性向上事例
社内エンジニアを設置することで、具体的にどのような生産性向上が期待できるのでしょうか。以下に、具体的な事例をいくつか紹介します。
-
RPA(Robotic Process Automation)の導入・運用: 定型的な事務作業を自動化することで、従業員の負担を軽減し、より創造的な業務に集中できるようになります。例えば、請求書の処理や経費精算などの作業を自動化することで、経理部門の業務効率を大幅に向上させることができます。
-
BI(Business Intelligence)ツールの導入・活用: 蓄積されたデータを分析し、経営判断に必要な情報を可視化することで、迅速かつ的確な意思決定を支援します。例えば、売上データを分析し、売れ筋商品や顧客層を特定することで、マーケティング戦略の立案に役立てることができます。
-
社内システムの開発・改善: 既存のシステムでは対応できない業務プロセスをシステム化したり、既存のシステムの使い勝手を改善することで、業務効率を向上させます。例えば、顧客管理システム(CRM)に、営業担当者が入力した顧客情報を自動的に分析し、最適なアプローチ方法を提案する機能を追加することで、営業活動の効率を向上させることができます。
-
情報共有基盤の構築: 社内の情報共有を促進し、コミュニケーションを円滑にすることで、従業員の連携を強化し、チームワークを向上させます。例えば、社内Wikiやチャットツールを導入することで、従業員が互いに質問しやすく、情報を共有しやすい環境を構築することができます。
これらの事例は、社内エンジニアが単にシステムを開発するだけでなく、業務プロセスを理解し、現場のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することで、企業の生産性向上に大きく貢献できることを示しています。

持続可能な組織運営のために
社内エンジニアの設置は、単に一時的な生産性向上に貢献するだけでなく、持続可能な組織運営にも不可欠です。なぜなら、社内エンジニアは、社内のノウハウや技術力を蓄積し、将来の技術革新に対応できる組織を育成する役割も担うからです。
例えば、社内エンジニアが、最新のプログラミング言語やクラウド技術を習得し、社内にその知識を共有することで、組織全体の技術力を向上させることができます。また、社内エンジニアが、オープンソースソフトウェアを活用し、自社独自のシステムを開発することで、外部ベンダーに依存しない自立的な組織を構築することができます。
このように、社内エンジニアは、技術的な側面だけでなく、組織文化の醸成や人材育成にも貢献し、企業の持続的な成長を支えることができるのです。

まとめ
日本企業がグローバルな競争に勝ち残るためには、IT投資の重要性を再認識し、社内エンジニアを積極的に設置する必要があります。社内エンジニアは、高度化、細分化、多様化するソフトウェアを駆使し、部門を横断的に活用できるツールやシステムを提供することで、企業の生産性向上に大きく貢献します。また、社内エンジニアは、社内のノウハウや技術力を蓄積し、将来の技術革新に対応できる組織を育成する役割も担い、企業の持続的な成長を支えることができます。今こそ、社内エンジニアの設置を検討し、生産性爆上げへの第一歩を踏み出すべきです。
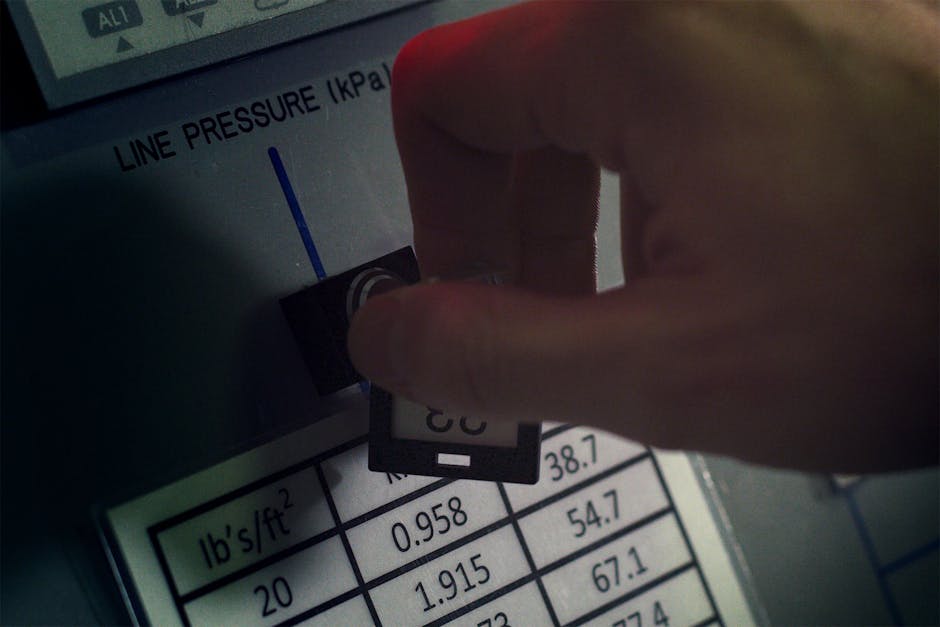



コメント