現代社会において、私たちはかつてないほど多くの情報に囲まれて生活しています。テレビ、新聞、雑誌といった従来のマスメディアに加え、インターネットの普及により、ニュースサイト、ソーシャルメディア(SNS)、動画共有プラットフォームなど、情報源は多様化の一途をたどっています。しかし、その一方で、メディア全体で見られる低俗化と劣化の傾向は、多くの識者や市民から深刻な懸念として指摘されています。
顕著に見られる低俗化・劣化の事例
メディアの低俗化・劣化は、具体的にどのような形で現れているのでしょうか。いくつかの事例を挙げることができます。
扇情主義とゴシップ報道の蔓延
視聴率やページビュー(PV)を稼ぐことを至上命題とするあまり、客観性や正確性を欠いた扇情的な見出しや、根拠の薄いゴシップ、個人のプライバシーを侵害するような報道が後を絶ちません。特にインターネットメディアでは、クリックを誘う過激なタイトルやサムネイルが溢れかえり、内容の伴わない、あるいは誤解を招くような情報が大量に流通しています。例えば、芸能人のスキャンダルを執拗に追いかけたり、事件の被害者や加害者の個人情報をセンセーショナルに扱ったりする報道は、社会的な議論を深めるどころか、人々の好奇心を煽り、時に偏見や憎悪を助長する結果を招いています。
フェイクニュースと情報汚染
意図的に作成された偽情報、いわゆるフェイクニュースの拡散も深刻な問題です。政治的な意図を持ったプロパガンダや、経済的な利益を目的とした詐欺的な情報が、SNSなどを通じて瞬く間に広がり、人々の判断を誤らせ、社会に混乱をもたらすケースが後を絶ちません。最近では、高度な技術を用いて生成されたディープフェイク動画などが登場し、何が真実で何が虚偽なのかを見分けることがますます困難になっています。ワクチンに関するデマの拡散による公衆衛生への影響や、選挙期間中における特定の候補者を貶める偽情報の流布などは、民主主義の根幹を揺るがしかねない重大な脅威です。
エンターテイメントの質の低下
報道だけでなく、エンターテイメント分野においても、質の低下が指摘されています。一部のテレビ番組では、内輪受けの過剰な演出や、出演者への配慮を欠いた企画、安易なドッキリや暴露話などが繰り返され、視聴者に深い感動や知的な刺激を与えるというよりも、瞬間的な笑いや驚きだけを追求する傾向が見られます。また、YouTubeなどの動画プラットフォームでは、過激な挑戦や迷惑行為を撮影した動画が注目を集めるなど、倫理観の欠如したコンテンツが散見され、特に若い世代への悪影響が懸念されています。

社会への影響:思考停止と分断の加速
このようなメディアの低俗化・劣化は、単に「面白くない」「質が低い」という問題に留まりません。専門家として、私はこれが社会全体に及ぼす悪影響を強く危惧しています。
第一に、人々の思考力の低下を招く可能性があります。表層的で扇情的な情報に慣れ親しむことで、物事の本質を深く考えたり、多角的な視点から情報を吟味したりする能力が衰えてしまう恐れがあります。複雑な社会問題を単純化し、白黒はっきりつけたがる風潮も、こうしたメディア環境と無関係ではないでしょう。
第二に、社会の分断を助長する危険性があります。フェイクニュースや偏向報道は、特定の集団に対する偏見や敵意を煽り、異なる意見を持つ人々との対立を深めます。SNSのアルゴリズムは、利用者の興味関心に合わせて情報を最適化するため、結果的に自分と同じ意見ばかりに触れる「フィルターバブル」や、閉鎖的なコミュニティ内で過激な意見が増幅される「エコーチェンバー」現象を引き起こしやすく、社会全体の対話や相互理解を困難にしています。
視聴者・利用者の責任:需要が供給を生むという現実
しかし、メディアの低俗化・劣化を、単にメディア側の問題として片付けることはできません。なぜなら、メディアが提供するコンテンツは、それを消費する視聴者や利用者の需要に応える形で形成される側面が強いからです。厳しい言い方になりますが、メディアの低俗化は、それを許容し、むしろ積極的に受け入れてきた私たち自身の「低俗化」「劣化」の鏡像であると言わざるを得ません。

クリック数と視聴率が支配する世界
現代のメディア、特にデジタルメディアは、クリック数、ページビュー、視聴時間、エンゲージメント率(いいね、シェア、コメントなど)といった指標によって、その成否が厳しく評価されます。広告収入に依存する多くのメディアにとって、これらの数字は死活問題です。そのため、コンテンツ制作者は、必然的に「数字を取れる」コンテンツ、すなわち、多くの人の関心を引き、瞬間的に強い反応を得られるコンテンツを優先的に制作するようになります。
その結果、たとえ内容が浅薄であっても、倫理的に問題があっても、扇情的で、ゴシップ的で、あるいは対立を煽るようなコンテンツが量産されることになります。「炎上マーケティング」という言葉があるように、意図的に物議を醸すような発信をして注目を集める手法が、一部で有効な戦略と見なされていることからも、この構造的な問題がうかがえます。質の高い調査報道や、深い洞察に富んだドキュメンタリーは、制作に時間とコストがかかる上に、必ずしも高い視聴率やPVに結びつくとは限りません。そのため、敬遠される傾向にあるのです。

私たち自身の選択がメディアを作る
私たちが日常的にどのようなニュースをクリックし、どのような番組を視聴し、どのようなSNSの投稿に「いいね」を押すか。その一つ一つの行動が、メディアが次にどのようなコンテンツを作るかの指針となっています。低俗なゴシップ記事が高いPVを獲得すれば、メディアは同様の記事をさらに量産するでしょう。過激な動画が高い再生回数を記録すれば、模倣するクリエイターが現れるでしょう。
つまり、メディアの低俗化・劣化に対して不満を言うのであれば、まずは私たち自身が、そのようなコンテンツを安易に消費していないか、無批判に受け入れていないかを省みる必要があります。情報を受け取る際に、その情報の質、信頼性、背景にある意図などを主体的に吟味する態度、すなわちメディアリテラシーが、現代を生きる私たち一人ひとりに求められています。視聴者・利用者がより質の高い情報を求め、低俗なコンテンツに対して明確に「NO」を突きつける姿勢を示すことが、メディアの質を向上させるための重要な鍵となるのです。
根源にある教育の問題:思考停止を招く「答え」偏重主義
では、なぜ多くの視聴者・利用者は、低俗なメディアコンテンツを無批判に受け入れてしまうのでしょうか。なぜ、情報の真偽を確かめたり、多角的に物事を捉えたりすることが苦手な人が増えているのでしょうか。その根源を探ると、私は現代の教育システムに潜む問題点に行き着かざるを得ません。それは、知識の詰め込みや、唯一の「正解」を効率的に見つけ出すことに偏重する教育のあり方です。

「正解」探しに終始する教育現場
現在の学校教育、特に受験を意識した教育においては、定められた知識をいかに正確に記憶し、テストで「正解」を導き出せるかが重視される傾向にあります。もちろん、基礎的な知識やスキルを習得することは重要です。しかし、問題なのは、そのプロセスにおいて、「なぜそうなるのか?」「他の考え方はないのか?」「この知識をどう活かせるのか?」といった、より本質的な問いを探求する機会が十分に与えられていない場合が多いことです。
画一的な評価基準に基づいたテストでは、多様な考え方や独創的な発想は評価されにくく、生徒は自然と「模範解答」や「効率的な解き方」を求めるようになります。教師もまた、限られた時間の中でカリキュラムを消化し、生徒の成績を上げることを求められる中で、マニュアル化された指導に頼らざるを得ない状況に置かれることがあります。このような環境では、生徒は自ら問いを立て、試行錯誤しながら答えを探求するという主体的な学びの経験を積むことが難しくなります。
その結果、多くの人が、「世の中には絶対的な正解が存在する」「専門家や権威のある人が言うことは正しい」「自分で考えるよりも、誰かが教えてくれる答えに従う方が楽だ」といった思考様式を無意識のうちに身につけてしまうのではないでしょうか。

「答え」を教えることの弊害
教育が「答え」そのものを教えることに終始してしまうと、学習者は受け身の姿勢になり、与えられた情報を鵜呑みにしやすくなります。複雑な問題に直面したときも、単純な二元論に飛びついたり、安易な解決策を求めたりする傾向が強まります。これは、まさに低俗なメディアが提供する情報(単純化された善悪、扇情的な見出し、一方的な主張など)を無批判に受け入れてしまう土壌を形成することにつながります。
自分で考えるプロセスを経験していないため、情報の真偽を疑ったり、異なる視点から物事を検証したりする習慣が身につきにくいのです。また、常に「正解」があるという前提に立つと、多様な価値観や意見が存在する現実社会において、他者との対話を通じて合意形成を図ることや、不確実な状況の中で主体的に判断を下すことが困難になる可能性もあります。
教育の本質:自ら「答え」を導き出す力を育む
では、本来の教育とはどうあるべきなのでしょうか。私は、教育の本質とは、単に知識や「答え」を教えることではなく、「答え」は自分自身の知識、経験、そして感情を通して、主体的に導き出すものであるということを教えることにあると考えます。言い換えれば、自ら問いを立て、情報を収集・分析し、多様な視点から物事を考察し、自分なりの結論や解釈を構築していくプロセスそのものを学ぶことが、教育の最も重要な目的なのです。
知識は思考の「材料」である
学校で学ぶ知識は、決してそれ自体が最終的な「答え」なのではありません。それらは、私たちが世界を理解し、問題を解決し、より良い未来を築いていくための、いわば思考の「材料」や「道具」に過ぎません。歴史の知識は現代社会の成り立ちを理解する手がかりとなり、科学の知識は自然現象を解き明かす鍵となり、文学や芸術は人間の感情や多様な価値観に触れる機会を与えてくれます。
重要なのは、これらの知識を断片的に記憶することではなく、それらを相互に関連付け、自分の経験や感情と結びつけながら、現実の課題に応用していく能力を養うことです。例えば、ある社会問題について考えるとき、歴史的な背景、経済的な要因、人々の心理など、様々な分野の知識を動員し、それらを統合的に考察することで、より深く本質的な理解に至ることができます。
育むべき能力:批判的思考力、多角的視点、共感力
自ら「答え」を導き出す力を育むためには、具体的にどのような能力が必要とされるのでしょうか。いくつか重要な要素を挙げることができます。
- 批判的思考力(クリティカル・シンキング):情報や主張を鵜呑みにせず、その根拠や妥当性を疑い、論理的に矛盾がないか、他の可能性はないかを検討する力。
- 多角的な視点:一つの事象を様々な角度から捉え、異なる立場や価値観を理解しようとする力。
- 共感力:他者の感情や経験を想像し、理解しようとする力。
- 創造性:既存の知識や枠組みにとらわれず、新しいアイデアや解決策を生み出す力。
- コミュニケーション能力:自分の考えを明確に表現し、他者と建設的な対話を行う力。
これらの能力は、従来の知識偏重型の教育だけでは十分に育まれません。探求学習、プロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)、ディベート、グループワーク、フィールドワークなど、生徒が主体的に課題に取り組み、試行錯誤し、他者と協働するような学習活動を積極的に取り入れていく必要があります。失敗を恐れずに挑戦できる環境や、多様な意見が尊重される雰囲気作りも不可欠です。
教育者と学習者の認識改革の必要性
教育の本質が「答え」を導き出すプロセスを学ぶことにあるならば、教育に携わる者(教育者)と教育を受ける者(学習者)双方の認識を根本から変える必要があります。現在の教育システムは、依然として「教育者は知識を授ける側、学習者はそれを受け取る側」という一方的な関係性を前提としている部分が大きいのではないでしょうか。
教育は知識伝達の一部に過ぎない
教育者は、自らが持つ知識やスキルが、学習者が自ら「答え」を導き出すための膨大な要素の中の、ほんの一部分を提供するに過ぎないという謙虚な認識を持つ必要があります。教師の役割は、単なる知識の伝達者ではなく、学習者の知的好奇心を刺激し、問いを引き出し、思考のプロセスをサポートするファシリテーター(伴走者)へと変化していくべきです。学習者が自ら課題を発見し、情報を収集・分析し、結論を導き出すプロセスを尊重し、時には共に悩み、共に探求する姿勢が求められます。
一方で、学習者もまた、教育を単に「答え」を教えてもらう場と捉えるのではなく、自らが主体的に学び、考え、問い続ける場であると認識する必要があります。受け身で知識を吸収するだけでなく、積極的に疑問を持ち、自分の意見を表明し、他者との対話を通じて学びを深めていく姿勢が重要です。分からないことや間違うことを恐れず、試行錯誤すること自体が学びの本質であると理解することが求められます。
認識改革なくして未来なし
この教育者と学習者の双方における認識の改革が進まない限り、教育は「答え」偏重の詰め込み型から脱却できず、自ら考える力を持たない人々を再生産し続けることになります。そして、そのような人々が増えれば、メディアが提供する低俗で扇情的な情報に無批判になり、それを安易に受け入れてしまう傾向はますます強まるでしょう。結果として、メディアの低俗化・劣化はさらに加速し、社会全体の思考力の低下や分断を深刻化させるという悪循環に陥ってしまいます。
教育現場における日々の実践の見直しはもちろんのこと、教育政策や社会全体の教育に対する価値観を変えていくことが急務です。
結論:教育改革なくしてメディアの健全化なし
本稿で論じてきたように、メディアの低俗化・劣化という現象は、単にメディア産業だけの問題ではありません。それは、そのようなコンテンツを需要し、受け入れてきた視聴者・利用者自身の質の低下と表裏一体であり、さらにその根底には、自ら思考し、「答え」を導き出す力を十分に育んでこられなかった現代教育の構造的な問題が横たわっています。
扇情的な見出し、フェイクニュース、質の低いエンターテイメントが蔓延る現状は、私たちが情報を主体的に吟味し、批判的に思考する能力を十分に発揮できていないことの現れと言えるでしょう。「正解」を効率的に覚えることに偏重した教育は、受け身で思考停止した人間を生み出しやすく、それが結果的に低俗なメディアを許容する土壌を作り出してしまっているのです。
この負のスパイラルを断ち切るためには、小手先の対策では不十分です。メディアリテラシー教育の重要性を訴えるだけでは足りません。より根本的な解決策として、教育そのもののあり方を問い直し、改革していく必要があります。
教育の目的を、単なる知識の伝達から、知識・経験・感情を統合し、自ら問いを立て、多様な視点から考察し、主体的に「答え」や「解釈」を導き出すプロセスを学ぶことへと転換しなければなりません。批判的思考力、多角的な視点、共感力、創造性といった、これからの時代に不可欠な能力を育む教育実践を、学校、家庭、そして社会全体で推進していく必要があります。
そのためには、教育者と学習者の双方が、「教育は知識伝達の一部に過ぎず、本質は自ら考える力を育むことにある」という認識を共有することが不可欠です。教える側と教わる側という固定的な関係性を超え、共に探求し、学び合う姿勢が求められます。
教育改革は、時間と労力を要する困難な課題です。しかし、この課題に取り組むことなしに、メディアの健全化、ひいては健全な市民社会の実現は望めません。自ら考え、判断し、質の高い情報を求め、建設的な対話ができる市民を育てること。それこそが、メディアの低俗化・劣化という現代社会の病理に対する、最も確実で本質的な処方箋なのです。教育の再生なくして、メディアの未来、そして私たちの社会の未来は開かれない、ということを強く訴えたいと思います。
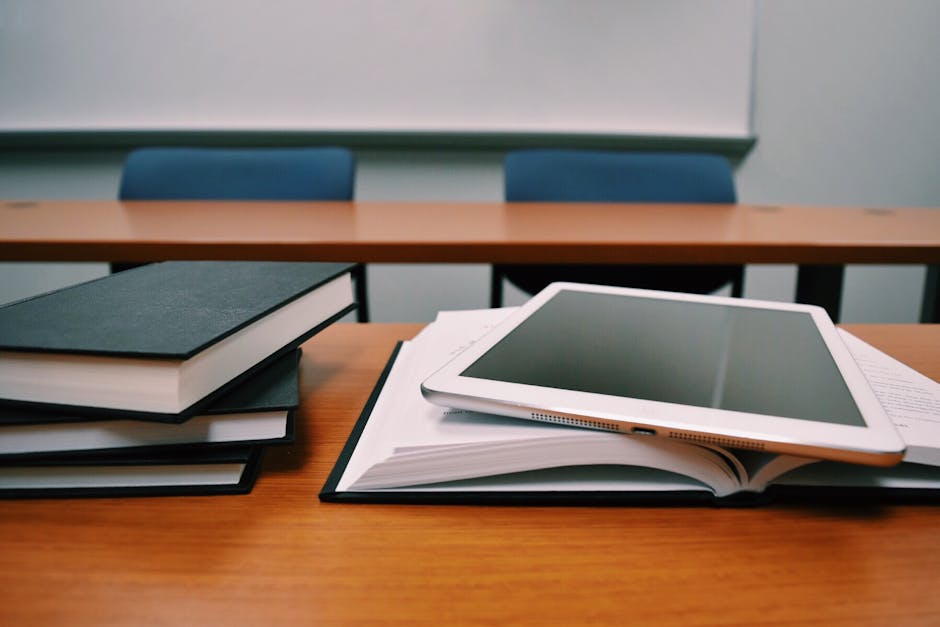
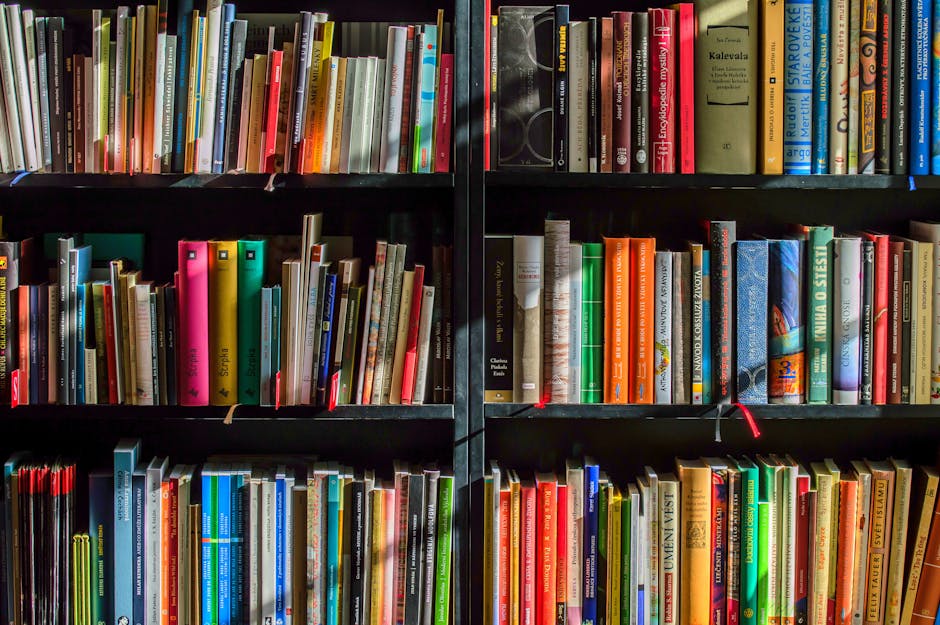


コメント