いじめは、子どもたちの健全な成長を阻害する深刻な社会問題です。いじめを受けた子どもは、心身に大きな傷を負い、その後の人生に深い影を落とすことがあります。特に、いじめの経験は「学習性無力感」と呼ばれる心理状態を引き起こす可能性があり、その影響は計り知れません。本稿では、いじめ問題と学習性無力感の関係について、事例を交えながら詳しく解説します。
学習性無力感とは何か
学習性無力感とは、アメリカの心理学者マーティン・セリグマンが提唱した概念で、「何をしても無駄だ」という感覚を学習してしまう状態を指します。セリグマンは犬を使った実験で、回避できない電気ショックを受け続けた犬が、その後、回避できる状況になっても逃げ出そうとしなくなることを発見しました。これは、犬が電気ショックから逃れることができないという状況を学習し、無力感を抱いてしまったためと考えられています。
学習性無力感は、いじめの被害者にも起こりやすい心理状態です。いじめられている子どもは、助けを求めても状況が変わらない、抵抗してもさらにひどい目に遭う、などの経験を繰り返すうちに、「自分は何をしても無駄だ」と感じるようになります。
いじめによる学習性無力感の事例
以下に、いじめによる学習性無力感の事例をいくつか紹介します。
-
事例1:小学校での継続的な無視
小学3年生のAさんは、クラスの一部の子どもたちから無視されるようになりました。最初は理由もわからず、Aさんは友達に話しかけたり、一緒に遊ぼうと誘ったりしましたが、無視は続きました。先生に相談しても、「仲良くするように」と注意されるだけで、状況は改善しませんでした。次第にAさんは、「自分は何をしても友達関係は良くならない」と感じるようになり、積極的に友達を作ろうとしなくなりました。授業中も発言を避け、休み時間は一人で過ごすことが多くなりました。
-
事例2:中学校での陰湿なネットいじめ
中学2年生のBさんは、SNS上でクラスメイトから誹謗中傷を受けるようになりました。最初は特定のグループだけだったものが、次第にクラス全体に広がり、Bさんの悪口を言うアカウントやグループが作られました。Bさんは、学校に相談したり、アカウントを削除したりしましたが、新しいアカウントがすぐに作られ、誹謗中傷は止まりませんでした。Bさんは、「何をしても意味がない」と絶望し、学校に行くのが苦痛になり、不登校になってしまいました。
-
事例3:高校での暴力的な金銭要求
高校1年生のCさんは、先輩から毎日のように金銭を要求されるようになりました。最初は少額だったものが、次第に高額になり、Cさんはアルバイトで稼いだお金を全て奪われるようになりました。Cさんは、先生や親に相談することを恐れ、一人で悩んでいました。先輩に抵抗しようとしたこともありましたが、逆に暴力を振るわれ、さらに脅されるようになりました。Cさんは、「抵抗しても無駄だ、逃げられない」と感じ、絶望的な気持ちで毎日を過ごしていました。
これらの事例からもわかるように、いじめは被害者に深刻な精神的苦痛を与え、学習性無力感を引き起こす可能性があります。
学習性無力感がもたらす影響
学習性無力感は、被害者に以下のような影響をもたらす可能性があります。
- 意欲の低下: 何をしても無駄だと感じるため、新しいことに挑戦する意欲を失い、積極的な行動を避けるようになります。
- 自信の喪失: 自分の能力や価値を否定的に捉え、自己肯定感が低下します。
- 抑うつ状態: 気分が落ち込み、悲観的になり、うつ病を発症するリスクが高まります。
- 社会性の低下: 人間関係を築くのが難しくなり、孤立感を深めます。
- 学業不振: 学習意欲が低下し、集中力が散漫になり、成績が低下します。
- 身体症状: 頭痛、腹痛、吐き気などの身体的な不調が現れることがあります。
学習性無力感は、被害者の心身に深刻な影響を与え、長期的にわたってその後の人生に影響を及ぼす可能性があります。
いじめ問題と学習性無力感への対策
いじめ問題と学習性無力感への対策は、早期発見、早期対応が重要です。
-
早期発見のために:
- 学校: 教職員はいじめの兆候に注意を払い、定期的なアンケートや面談を実施し、子どもたちの状況を把握するように努める。
- 家庭: 保護者は子どもたちの様子を注意深く観察し、変化に気づいたら、話を聞き、寄り添う姿勢を示す。
- 地域: 地域住民はいじめを目撃した場合、学校や関係機関に連絡するなど、積極的に関わる。
-
早期対応のために:
- 学校: いじめが発覚した場合、迅速かつ適切な対応を行う。いじめの加害者、被害者の双方に対して、カウンセリングや指導を行い、再発防止に努める。
- 家庭: いじめの被害にあった子どもを励まし、安心できる環境を提供する。必要に応じて、専門機関に相談し、適切な支援を受ける。
- 専門機関: 臨床心理士や精神科医などの専門家は、いじめの被害にあった子どもに対して、カウンセリングや心理療法を行い、心のケアを行う。
-
学習性無力感への対策:
- 成功体験の積み重ね: 小さな目標を設定し、達成することで、自己肯定感を高める。
- 認知行動療法: 否定的な思考パターンを修正し、現実的な考え方を身につける。
- 周囲のサポート: 家族や友人、先生など、信頼できる人に相談し、支えてもらう。
- 自己肯定感を高める活動: 趣味やスポーツなど、自分が楽しめる活動を見つけ、積極的に取り組む。
まとめ
いじめ問題は、被害者に学習性無力感という深刻な心理状態を引き起こす可能性があります。学習性無力感は、被害者の心身に大きな影響を与え、その後の人生に影を落とすことがあります。いじめ問題と学習性無力感への対策は、早期発見、早期対応が重要であり、学校、家庭、地域が連携して取り組む必要があります。いじめのない社会を実現するために、私たち一人ひとりが意識を高め、行動していくことが大切です。
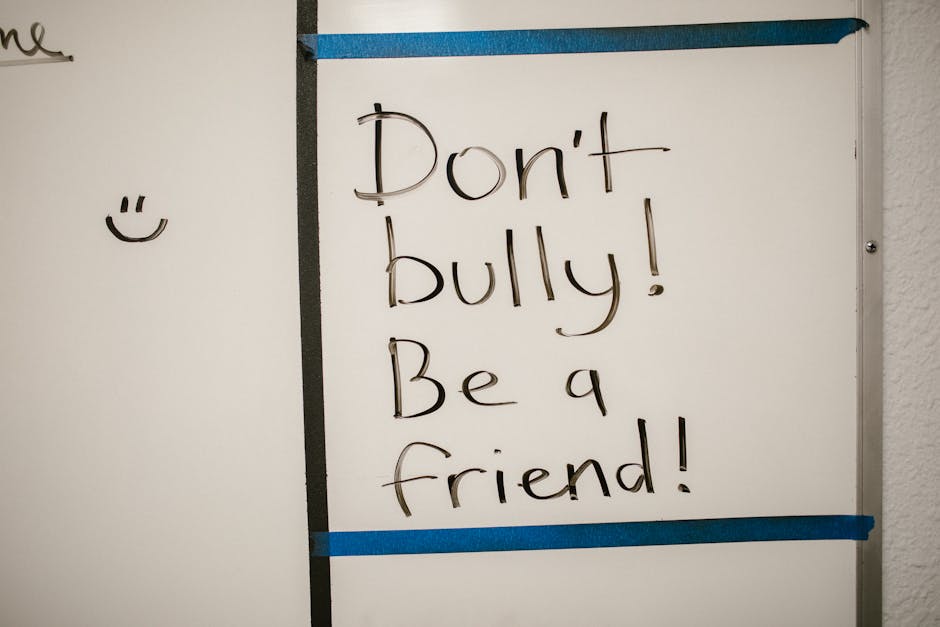


コメント